介護老人保健施設
2025-08-21
「頭の中の図をそのまま形にできる!」ペースノートで情報共有がしやすくなり、稼働率と職員の意識が向上

- 施設名:
- 介護老人保健施設 アルカディアウエル
- 所在地:
- 宮城県亘理郡山元町山寺字堤山8-5
- ベッド数:
- 100
- 相談員数:
- 5
- 課題
- 入退所スケジュール管理、情報共有、業務効率化
目次
エクセルで入退所を管理し、紙で共有することの課題
まずは医療法人 育志会様について教えてください。
私ども医療法人 育志会は、宮城県亘理郡山元町にて、介護老人保健施設「アルカディアウエル」、短期入所生活介護「プログレス」、指定居宅介護支援事業所「ランディング」を展開しており、総合的な地域医療を提供する「ひらたクリニック」もあります。
グループホーム1軒とケアハウス1軒を運営する社会福祉法人 紀心会もあり、連携を図っています。
アルカディアウエルは、それまでこの地域にはなかった「高齢者が自分の生まれ育った町で支えあい、いきいきと暮らせる介護老人保健施設」として、平成8年に創設されました。
利用者や家族の「~したい」を尊重し、一人ひとりのニーズを叶える施設を目指しています。リハビリだけでなく、様々なイベントや他者と交流する生活を満喫してもらうことで、スムーズに元の生活につなげられることが目標です。
ベッド数は100床で、ショートステイとしても活用しています。それとは別に、ショートステイだけを提供する施設がすぐ向かいにあります。職員数は約100名で、うち相談員は5名です。ペースノートはその5名が編集権限で使っています。そのほか、現場の職員は各部署に置いてあるパソコンでペースノートを閲覧しています。
ペースノートを導入する前にはどのような課題があったのでしょうか?
もともとエクセルで入退所スケジュール管理をしていたのですが、ベッド数が100床あるので、エクセルの表ではひと目で空床を把握することは難しく、ベッドの移動も見えづらかったのです。
「この日空いていますか?」と問い合わせをいただいても、100床分のセルを上から順番に見ていかないと返事ができなくて……。
以前、別の施設に勤めていたときに、A3用紙に入退所スケジュールを鉛筆で書き込んだり消しゴムで消したりする、ペースノートの手書きバージョンのようなものを自作していたんです。
そのやり方は「誰がどの部屋に入っていて、どこへ移動するのか」を把握しやすかったものの、ベッド数が100床あり相談員が5人いるこの施設で採用するのは現実的ではありません。
だからエクセルを使っていたわけですが、自分の頭の中にあるものを簡単にみんなに見える形にできたらいいのに、という想いはずっとありました。
エクセルの入退所表は、ほかの相談員や現場の職員にはどう共有していたのですか?
エクセルの入退所表を相談員5人で共有して全員で編集していたわけではありません。
席の近い人にはパソコンの画面上でエクセルを表示してやりとりすることはありましたが、複数人で1つのファイルを共同編集することはなく、作成した表を印刷して紙で共有するのが基本でした。
現場の職員に対しても、やはり印刷した紙を届けていました。
この方法の問題は、変更があったときに伝えづらいことです。当施設は、多い月で入退所者が30名ほどで、予定の変更や部屋移動は毎日のようにあります。
事務室と現場が離れているので、その都度、印刷した入退所表を持って確認に行って、話を聞いて戻ってきてエクセルを修正し、再度印刷して届けにいかなくてはなりません。
細々した調整が行き交うなか、「どちらの紙が最新情報なの?」「どこが変わったの?」と聞かれることも多く、相談員と現場の双方がコミュニケーションにかなりの時間を取られる状況でした。
また、部屋移動が伝わらず二重予約が起こったり、空床を把握できないために積極的な働きかけができず、稼働率が下がってしまったりするのも大きな問題でした。

ペースノートの第一印象は「こんなシステムがあったのか!」。
ペースノートを知ったきっかけと第一印象をお聞かせください。
ペースノートを知ったのは、2024年11月に岐阜県で開催された全国老健大会の出展ブースです。そのときは別目的で参加していたのですが、偶然話を聞いて、「自分が頭の中で思い描いていたものがシステムとして存在していたのか」と驚き、これを使えばきっとベッド調整が楽になると確信しました。
それまで、稼働率を大きく左右する入退所スケジュール管理の方法は、門外不出というか、各施設の知見を集めたクローズドなものだと思っていたんです。だから入退所スケジュールに特化したシステムがあるなんて考えもせず、探してみることもありませんでした。
実際の操作画面も覚えやすく使いやすいと感じましたし、「ペースノートを使って情報共有をすれば、ご利用者にとって使いやすい施設になる」と判断できたため、施設に戻ってすぐほかの相談員に伝え、経営層にも導入したいと相談しました。
上申はスムーズにいきましたか? 導入までの経緯を教えてください。
最初は老健とショートの両方で使おうと考えたのですが、ショートよりも老健の方がメリットが大きいと感じましたので、まずは老健での利用を考えました。他の相談員もぜひ使ってみたいという反応でした。
それまで自分の頭の中だけで把握して回していたものが形になっている、とても良いツールであると思いましたし、エクセルで管理できる人が辞めたら回らなくなる属人的なやり方ではなく、みんなが等しく簡単に使えるシステムを導入するべきだと経営層に話を持ちかけました。
無料トライアルで相談員と現場の職員にも使ってもらって好感触だったこともあり、「相談員、現場職員、ご利用者にとってこんなにいいシステムを使わない手はない」と必死に動いて経営層にも理解してもらい、2025年1月、ペースノート導入に至りました。

導入前の課題が解決でき、空床FAXの送信で稼働率も向上
ペースノートを使うようになって、どのように感じていますか?
エクセルとは全然違って、とても使いやすいです。頭の中にある部屋とベッドのイメージのまま、直観的にクリックとドラッグで操作ができるので、すぐ馴染めました。
ペースノートの編集権限は相談員だけに付与していますが、現場の各部署でも閲覧できるようにしているので、もう紙に印刷して現場に持っていき、変更のたびに行ったり来たりするようなことはありません。
ベテランの相談員でないと、エクセルの表の意図や見方を現場に伝えるのは難しいんです。でも、ペースノートなら見やすい画面で、現場の職員にも伝えやすく、ベッド調整をする上でとても助かっています。
また、現場の職員がペースノートを閲覧することで先の予定を見通せるようになり、稼働率などの数字に意識的になったのも嬉しい変化です。情報共有の仕方が変わり、「見える化」ができたことで、みんなの意識も変わったのだと感じています。
仮予約などの予定を入れた時など、日々の業務を先回りしてくれるようになり、相談員としてはスケジュールが見えすぎて困ってしまうくらいですね。(笑)
導入前の課題はどれぐらい解決できましたか?
かなり解決できたと感じています。以前は空床をリアルタイムで正確には把握できていませんでしたが、今はひと目でわかるので、問い合わせに対してすぐに対応できるようになったのが、大きな改善点だと思います。
また、空床を把握できないために積極的な働きかけができず、稼働率が下がってしまう時期があったのも課題でしたが、ペースノートのFAX送信機能で、居宅と病院への空床FAXを自動作成・送信できるようになったので、問い合わせの電話が大幅に増えました。ショートステイの利用者も増加しています。
もちろん、営業をする上で実際に訪問し顔を見て話をすることは大切です。ペースノートを導入する前は、営業には必ず足を運んでいました。しかし、訪問できる場所には限りがありますし、行ったとしても先方が忙しくて対応してもらえないこともあります。
その点、ペースノートは最大600通まで追加料金なしで送れるので、FAXを月に2回定期的に送ることで空き状況を伝えられ、「いま空床があるのなら使いたい」と電話をいただけるようになりました。
これからも訪問営業と並行してFAX送信を続けていきたいです。
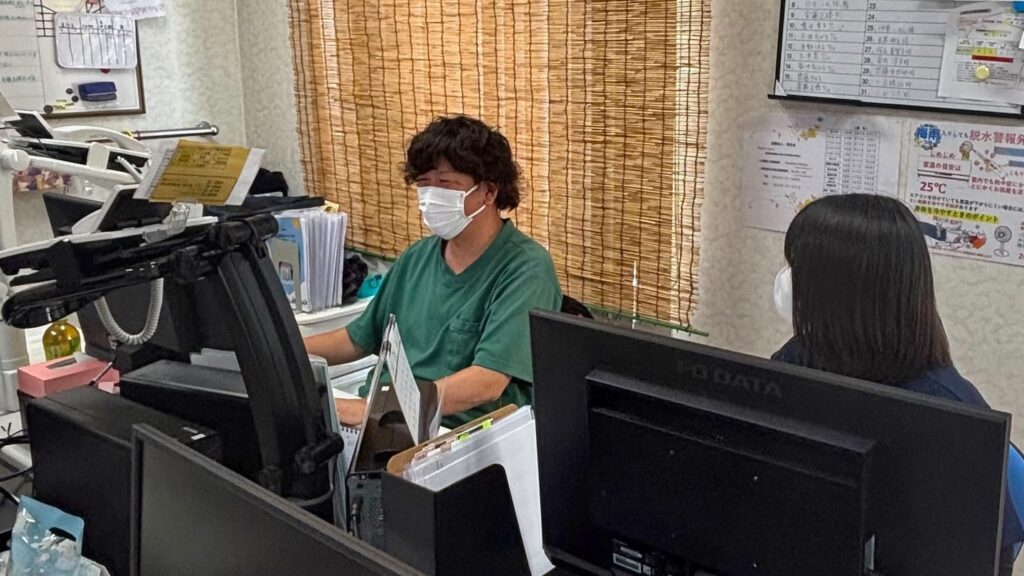
より良い施設運営に貢献してくれるペースノート。
ペースノート社のサポート体制やシステム開発の姿勢について、どう感じていますか?
最初に問い合わせをしたときから、とても親切な会社だなと感じています。導入時の設定もしてもらえましたし、カスタマーサービスから定期フォローアップがあるので、サポート体制については十分満足しています。
すごくいいと思っているのは、定期フォローアップの際に「この部分をこんなふうにできませんか?」と相談すると、こちらの課題にとても寄り添ってくれることです。
何か要望を伝えても、「開発部に伝えておきます」というだけで改善はしてくれない会社もあります。でも、ペースノート社は、できることであればすぐに対応してくれますし、技術的に難しい場合はそれを率直に伝えた上で、代案を出してくれます。
「要望を伝えたら、ちゃんと変わるんだ」と思えたのは、ペースノート社が初めてでした。
これからペースノートの導入を検討している方のアドバイスをお願いします。
ペースノートは、自分の頭の中にある図がそのまま表示できるのがとても良いです。正直、こんなシステムがあるなんて思ってもいませんでした。
施設運営には稼働率や在宅復帰率などの「見える化」が非常に大事なので、特に超強化型の事業所には、情報共有ツールとしてペースノートをおすすめしたいです。稼働率の向上は、ご利用者の役に立てるだけでなく、職員の働きやすさにも直結すると思います。
最後に、今後の展望やペースノート社への期待をお聞かせください。
「CAREKARTE(ケアカルテ)」のような他社請求ソフトとのデータ連携が拡がっていくことに期待していますし、引き続き、私たちの課題に寄り添い、施設にとって使いやすいツールであり続けられるよう、努力していただけると嬉しいです。
今のところ、近隣でペースノートを使っている事業所は多くありません。ですから、ペースノートの活用事例を老健大会で発表し、育志会の介護老人保健施設アルカディアウエルではこういうことをしていると広めたいと思っています。




